発達プログラム144号 「一冊まるごとコロロメソッド!自閉症・発達障害Q&A」より
家族も支援者も、一般の方々の中に、このような考えがあることは、承知をしておかなければなりません。
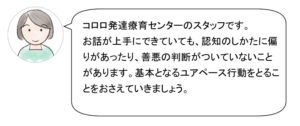
善悪判断【ユアペースを獲得するには】
の記事をご紹介します。
Q.二十歳になる自閉症の息子は、作業所に徒歩で、一人通所しています。
帰途中で、神社の賽銭箱からお金を盗もうとしたところを見つかり、管察に通報されてしまいました。
未遂でしたので、すぐに帰されましたが、「もうしません」とは言うものの心配です。
本人の自立のためには、一人で行動する練習は必要だと思いますが、外出時に、してはいけないことを教えるには、どのようにしたらよいでしょうか。
A
年齢が上がれば、行動範囲も広がます。
友人や介護者と外出したり、一人で行動したりする機会が増えることは、自閉症者の自立へのステップとして望ましいことと思います。
しかし、一方で、深刻なご相談も増えています。
バス車内で、女性の髪の匂いを嗅ぎ、痴漢と間違えられたり、ホームで非常ボタンを押して電車を止めてしまったりと、現実に多くのトラブルが発生しています。
息子さんの行為は、明らかに犯罪です。
今回、発覚したことが幸いと思って、二度と同じ過ちをさせないよう、療育的視点から、今後の対応プログラムを考えていきましょう。
善悪判断の未熟さ
既に時間が経ってから、懲罰的に叱っても、何を叱られているか理解できずに、問題行動を繰り返してしまうことがよくあります。
しかし、息子さんの場合は、余罪の可能性も否定できませんから、今回が初めてか、盗もうとした理由、賽銭箱からお金が盗めることを何で知ったのか、当日の経緯などを説明させ、厳重注意すべきでしょう。
この時、親御さんが感情的になり、強い口調で問いただすと、息子さんの方も自己防衛が強く働き、作話をしたり、ことば尻に反応して、謝罪のことばを繰り返すだけになりやすいものです。
そこで、ノートに、状況をたずねるための質問を書き、息子さんにも、文章で答えさせるようにしてみましょう。
答えが、事実か作話か、日頃の素行を知る親御さんであれば、ある程度は判断できることと思います。
この過程は、親御さんが、質問のやりとりを通して、息子さんの罪の意識がどの程度なのかを知るために必要です。
その結果、親御さんの予想以上に、物事の善し悪しの理解が幼いことに驚かれるかもしれません。
仮に判断できたとしても、その理由付けは「お母さんが怒るから」「いけないことだからいけない」など、幼いレベルで留まりがちです。
その現実を知ることにより、今、何を教えるべきか見えてくると思います。
外出時にしてはいけないことを教えるために、まず善悪判断の学習に取り組んでみましょう。
「してよいこと」「いけないこと」を、書き出させ、その理由を教えていくのです。
さらに、約束文を書かせ、それを遵守させる方法を作業所側と話し合っていきましょう。
欲求の自己コントロール
家庭での過ごし方も見直しが必要です。
学校時代に比べてマイペースに過ごすことが増えていませんか?
一日仕事をしてきたのだから、家では好きに過ごさせてあげたいと、お考えかもしれません。
しかし、自閉症者の場合、欲求や要求が常に認められているようなマイペースの時間が長いと、適応力は下がります。
そうすると、外で何か欲求が生じた時、すぐにやらなければ気が済まない反射的行動が増えてしまいます。
今回も、同様だったのではないでしょうか。反射的行動ですから、善悪の判断をする以前に行動を起こしてしまったのです。
家庭では、ユアペース行動が基本です。帰宅後は、家事を手伝う、欲しい時には、家族に一言断わる、ゲーム等好きなことは時間を決めてする等々、家庭のルールを守って生活させるようにしましょう。

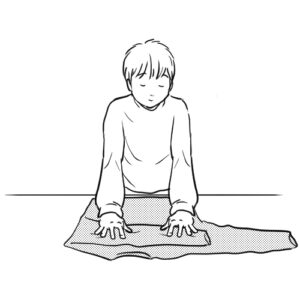

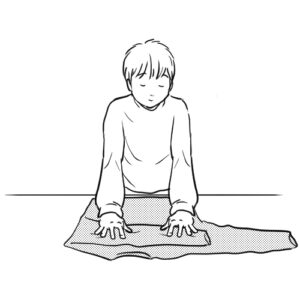
ユアペース獲得は歩行から
息子さんは、お母さんと同じ歩調で1時間歩き続けることは出来るでしょうか?
「歩行」は、療育の基本課題です。ユアペース状態を維持するためには、何歳になっても「歩行トレーニング」が必要です。
相手や、集団に合わせて、同じペースで歩くことは、様々な場面で、他者の存在を意識することにもつながります。
また、時には帰宅途上、どのような姿や表情で歩いているかのチェックが必要です。
待ち伏せして、声をかけ、常に親御さんが見ているという緊張感を持たせておくこともぜひ、取り組んでいただきたいと思います。
家族、支援者に求められるものある障害福祉関係のブログに、次のような意見がありました。
「差別をするつもりはないが、少なくとも自分を制御できない障害があるなら、一般社会へ出すときには、迷惑をかけないよう十分監視体制を取るべき。もしできないなら、外に出さない方がよい」
家族も支援者も、一般の方々の中に、このような考えがあることは、承知をしておかなければなりません。
何か事件を起こしても、本人に責任能力はありません。
しかし、もし相手側を傷つけたり、大きな被害を与えるような事態になれば、「自立のため」という理由で、相手側は納得するでしょうか。
本人や家族にとっても悲劇です。
自立をサポートするためには、最悪の事態を予見する眼を持ち、今取り組むべき療育課題は何かを考えていく必要があります。
この記事をご紹介したのは、
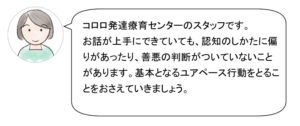
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




