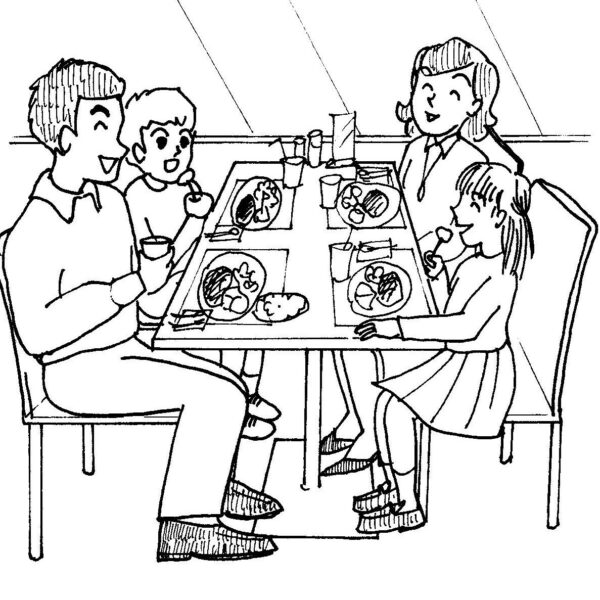高機能自閉症児への認知特性をふまえた関わり方 事例1 の記事をご紹介します。
高機能自閉症児と話をし、内面にふれると、こんな考え方をしていたのかとハッとさせられることが多々あります。
それは、個性という言葉では済ますことのできない認知の特性からくるものです。
周囲から誤解を受けやすい、彼らの生きにくい認知の特性とはどのようなものか、ご紹介したいと思います。
事例1(中学1年 高機能自閉症男児)
一般級在籍のK君はいつも学校に遅刻をします。
ご両親は、遅刻をしてはいけないと何度も話し聞かせていましたが、一向に良くなる気配はありませんでした。
ご両親よりコロロでも指導してほしいということで、K君の遅刻に対する概念はどういうものか聞いてみることにしました。
先生「遅刻は良いことですか?」
K君「悪いことです」
先生「では、週に何回ぐらいの遅刻なら良いと思いますか?」
K君、ちょっと考えて「1回くらいは良いと思います」
先生「週に1回遅刻したら、月に何回の遅刻ですか?」
K君「4回です」
先生「月に4回の遅刻は多いですか?少ないですか?」
K君、首を傾げる。
先生「では、月に4回の遅刻をしたら、1年間で何回遅刻をすることになりますか?」
K君、間髪入れずに「48回です」
先生「1年間に48回遅刻をするのは、多いですか?少ないですか?」
K君、自信ありげに「多いと思います」
先生「もう一度聞くけど、週に何回の遅刻なら良いと思いますか?」
先生「もう一度聞くけど、週に何回の遅刻なら良いと思いますか?」
K君「それはやはり0回か多くても1回が良いと思います」
先生「遅刻が48回ある人は、高校に合格すると思いますか?」
K君「・・・」
先生「遅刻が多い人は高校に合格しません。高校に行きたい人は遅刻しないようにしましょう」と話しました。
K君は、ご両親や先生に遅刻はしてはいけないことを教えられて、口では「遅刻は悪いことだ」と言っていても、
遅刻に対してちょっと違う聞き方で聞くと、週に1回は遅刻しても良いと答えました。
これでは、遅刻はいけないという概念が本当にあるとは言えません。K君が遅刻をしてしまうのも頷ける気がしました。
そこで、毎日遅刻をしたら、1学期だけでも100回近くになってしまうことをK君にイメージさせ、
高校に入りたいという未来の欲求はどれくらいかを知るため、次の回まで様子を見ることにしました。
2か月後、ご両親より遅刻の回数がかなり減ったとご報告を受けました。
「遅刻が多いと高校の内申が悪くなることを話して聞かせたのが良かったのだと思います」ということでした。
私も、K君が遅刻をしなくなったことが嬉しくて早速褒めました。
そして、どうして急に遅刻の回数が減ったのか理由を知りたくて、再度K君に聞いてみました。
先生「遅刻しなくなったらしいね。どうして、遅刻しなくなったの?」
K君「電車で先生と会う約束をしたから」
先生「?」「どんな約束をしたの?」
K君「〇時〇分の〇両目の電車に乗れば、先生は必ずそこにいるから一緒に学校に行こうと言われました」
なるほどK君の場合、〇時〇分までに学校に来なさいという一般的な規則では、
朝起きて学校に行くまでの目的行動に繋がることはできず遅刻していたのです。
小学時は、登校班があり、〇時〇分に〇〇で集合するというK君にとっては明確な目的がありました。
今回、「〇時〇分発の〇両目で会おう」と一対一で先生に具体的に言われたのは、K君にとってとてもわかりやすく、
小学校同様、朝の支度の目的行動に移せたのでしょう。
聞けば、その約束をしてくれた先生は担任の先生ではないらしく、臨機応変な先生の指導に感謝しました。
結果的にK君は遅刻しなくなったのですが、彼にとってみれば、遅刻しない時間に学校に着いただけのことです。
遅刻はいけないから間に合う時間に家を出ようという、より高度な概念を持つのはまだ先のようです。
また、高校の内申書が悪くなるからと説得されても、それ自体イメージできません。
遅刻をしなくなり、色々話せるからといっても、遅刻はいけないという概念はまだ構築されていないのです。
そのことをご両親にお話しし、まずは〇時〇分までにお弁当を食べ終える等の指示をきいて、
時間を意識した、少し急いだ行動がとれることを課題とし、家でも行うよう宿題にしました。
朝起きて学校に行くまでの行動は、やるべきことがたくさんあります。
一対一対応で「〇分までに~する」という行動がとれるようになったら、少しずつ行動を増やしていくことで、
最終的には〇時〇分までに学校に着くということをできる様にしたいと思っています。


この記事をご紹介したのは…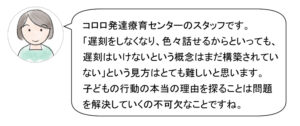
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎