〈コラム〉マナーを身につけるための身体づくり⑵
発達プログラムNo.
2発達障害児の体に残る反射
3体に反射が残った場合の不自由さ
4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング
5座っていられる時間を伸ばす方法
6静かに待てる身体にするために
それは、「歩行トレーニング」です。
療育者である大人が子どもと手をつないで足裏反射による飛び跳ねやつま先歩き、手放し反射を抑えながら歩き続けることです。
手をつないで歩けなかった子どもが、大人と手をつないで1時間~1時間半歩けるようになると、
その手つなぎをした大人との関係も必ず良好になります。
マナーを守って社会生活を送っている青年を育てたお母さんに歩行のことを伺うと、
どの方もコロロに通室するようになってから、ほぼ毎日歩行トレーニングをしています。
また、コロロの行事であるハイキングや、合宿等も必ず参加されていました。
今回のテーマである外出マナーを、マイペースな子どもに教えることはほぼ不可能です。
しかし、毎日歩行トレーニングをしていくことで、人の認知が薄いマイペースな状態から、
手つなぎをして反射を抑えてくれる大人を意識できるようになり、ユアペース(受け身)の体が少しずつできてきます。
これが、マナーを守った行動を教えるための下地となります。
歩行トレーニングで注意して頂きたいのは、歩行中に自動販売機を触らせたり、葉っぱや枝、道に落ちているものを拾わせたりしないことです。
お散歩気分で子どもの好きなように歩かせてもユアペースにはなりません。
目についたものに飛び出していってしまうのは、目と体の分化ができていないためです。
見て、触りたいと思った時にはもう体が動いて触っているといった状態では、とても冠婚葬祭には参加できないでしょう。

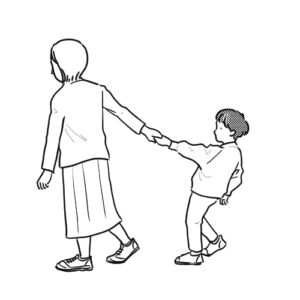
〇良い歩行 ×ひっぱられ歩行
また、ひっぱられ歩行は自立歩行ではないので、自分で重心の保持ができるようになりません。
子どもを重力に負けず歩ける体にするには、山登りが一番効果があります。
手放し反射や脱力に加えてマイペースな子どもを歩行トレーニングさせるには、親もかなりの忍耐が必要になってきますが、
とにかく逃げずに向き合っていくしかありません。
子どもが拒否してできない時は、必ずスモールステッププログラムが必要なので、コロロスタッフに相談してみてください。
まず始めに行ったことは、手をつないで歩き、リズム運動に参加することでした。
もちろんA君は手放し反射があり、脱力もしますが、尻ピョン反射を利用して、
脱力しそうなタイミングでこちらがお尻を触るとまた歩き始めるということを繰り返して歩けるようになってきました。
今までのA君は反射で動いていたので、いくら動いても疲れ知らずでしたが、反射を抑えて人に合わせて動くのはかなり疲れるのでしょう。
10分ほど歩いたら、A君自ら椅子に座ろうとしました。
しめしめと思いそのまま椅子に座らせ、他の子ども達も一緒に、視覚教材を次々と見せる集会をしました。
本来黒子スタッフは後ろから反射をとめるのが通常ですが、その子の場合は、肩を触られるとのけぞり反射を誘発してしまうため、
黒子は前で胸のあたりをトンと触って尻ピョン反射を止めると、視覚教材を見ながら1分座り続けることができました。
体がもぞもぞしてきたところでまたりズム運動をして、疲れた頃にまた座らせて集会をする、ということを繰り返しました。
その後、戸外歩行に1時間行くと、その日のうちに15分座っていられるようになりました。
このように、着席時間を伸ばすためには、まずは手をつないで歩ける体にすること、
座らせた時に必ず見せるものを用意すること、そして、尻ピョン反射を抑える黒子の存在が必要です。
家でテレビを見る時も、動きながら見ていたり、テレビに触って見ていては、目と体の分化は促されません。
また、自閉症の子どもは、好きな物を見ているときに独特の反射が出てきます。
興奮すると、手が突っ張っていたり、ピョンピョン跳ねてしまうこともあるでしょう。
これを嬉しがっている時の表現として放置せずに、親がリビングで黒子として上手に反射を止めてあげて、
手はお膝にして椅子に座らせ続けることが、嬉しい気持ちと体の分化を促し、目と体の分化も促します。
30分くらいは椅子に座っていられる体に育てていきましょう。
中略
見るものがあれば、30分くらいは座っていられるようになったら、何もない状況でも、体を止めて少し待っていられるように練習をしましょう。
コロロでは「行動トレーニング」と呼んでいますが、正座、イス着席、立位などの、一定の姿勢を保持する練習です。
立ち位置、座り位置をわかりやすくし、最初は10秒から、徐々に時間を延ばし、5分、10分、できれば20分くらいは一定の姿勢を保っていられるように練習します。
これができるようになったら、口の常同行動(独語)を止める練習を始めましょう。
独語の多い子は上下の唇を閉じ続けることができません。
その場合は、コインやカードを口唇にはさむ練習をします。
口唇を閉じ続けられる体を作っていくのです。10ヵウントから少しずつ伸ばしていきます。

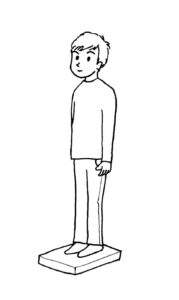
正座 立位
飛行機に乗って旅行したり、映画を見たりなど、静かに過ごせるようになることは子どもの生活の幅を広げます。
子どもが自分で体をコントロールできるようにするための行動トレーニングが、
ゆくゆくはマナーを身につける身体をつくっていくということがおわかりいただけたら幸いです。
この記事をご紹介したのは…
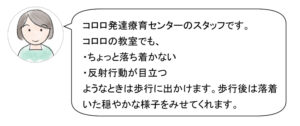
135 外出のマナー―トラブルを防ぐ―
より前回に引き続き、マナーを身につけるための身体づくりの記事をご紹介します。
1姿勢よく座っていられない子どもたち2発達障害児の体に残る反射
3体に反射が残った場合の不自由さ
4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング
5座っていられる時間を伸ばす方法
6静かに待てる身体にするために
4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング
色々持っている体の反射を減らしつつ、体幹を作ってくれる最高の基礎トレーニングがあります。それは、「歩行トレーニング」です。
療育者である大人が子どもと手をつないで足裏反射による飛び跳ねやつま先歩き、手放し反射を抑えながら歩き続けることです。
手をつないで歩けなかった子どもが、大人と手をつないで1時間~1時間半歩けるようになると、
その手つなぎをした大人との関係も必ず良好になります。
マナーを守って社会生活を送っている青年を育てたお母さんに歩行のことを伺うと、
どの方もコロロに通室するようになってから、ほぼ毎日歩行トレーニングをしています。
また、コロロの行事であるハイキングや、合宿等も必ず参加されていました。
今回のテーマである外出マナーを、マイペースな子どもに教えることはほぼ不可能です。
しかし、毎日歩行トレーニングをしていくことで、人の認知が薄いマイペースな状態から、
手つなぎをして反射を抑えてくれる大人を意識できるようになり、ユアペース(受け身)の体が少しずつできてきます。
これが、マナーを守った行動を教えるための下地となります。
歩行トレーニングで注意して頂きたいのは、歩行中に自動販売機を触らせたり、葉っぱや枝、道に落ちているものを拾わせたりしないことです。
お散歩気分で子どもの好きなように歩かせてもユアペースにはなりません。
目についたものに飛び出していってしまうのは、目と体の分化ができていないためです。
見て、触りたいと思った時にはもう体が動いて触っているといった状態では、とても冠婚葬祭には参加できないでしょう。

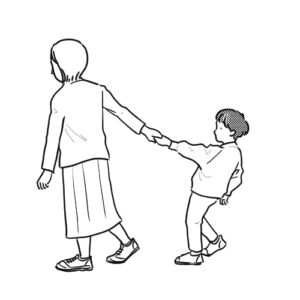
〇良い歩行 ×ひっぱられ歩行
また、ひっぱられ歩行は自立歩行ではないので、自分で重心の保持ができるようになりません。
子どもを重力に負けず歩ける体にするには、山登りが一番効果があります。
手放し反射や脱力に加えてマイペースな子どもを歩行トレーニングさせるには、親もかなりの忍耐が必要になってきますが、
とにかく逃げずに向き合っていくしかありません。
子どもが拒否してできない時は、必ずスモールステッププログラムが必要なので、コロロスタッフに相談してみてください。
5座っていられる時間をのばす方法
先日会った4歳の超多動の自閉症児A君は、2秒たりとも座っていることができませんでした。まず始めに行ったことは、手をつないで歩き、リズム運動に参加することでした。
もちろんA君は手放し反射があり、脱力もしますが、尻ピョン反射を利用して、
脱力しそうなタイミングでこちらがお尻を触るとまた歩き始めるということを繰り返して歩けるようになってきました。
今までのA君は反射で動いていたので、いくら動いても疲れ知らずでしたが、反射を抑えて人に合わせて動くのはかなり疲れるのでしょう。
10分ほど歩いたら、A君自ら椅子に座ろうとしました。
しめしめと思いそのまま椅子に座らせ、他の子ども達も一緒に、視覚教材を次々と見せる集会をしました。
本来黒子スタッフは後ろから反射をとめるのが通常ですが、その子の場合は、肩を触られるとのけぞり反射を誘発してしまうため、
黒子は前で胸のあたりをトンと触って尻ピョン反射を止めると、視覚教材を見ながら1分座り続けることができました。
体がもぞもぞしてきたところでまたりズム運動をして、疲れた頃にまた座らせて集会をする、ということを繰り返しました。
その後、戸外歩行に1時間行くと、その日のうちに15分座っていられるようになりました。
このように、着席時間を伸ばすためには、まずは手をつないで歩ける体にすること、
座らせた時に必ず見せるものを用意すること、そして、尻ピョン反射を抑える黒子の存在が必要です。
家でテレビを見る時も、動きながら見ていたり、テレビに触って見ていては、目と体の分化は促されません。
また、自閉症の子どもは、好きな物を見ているときに独特の反射が出てきます。
興奮すると、手が突っ張っていたり、ピョンピョン跳ねてしまうこともあるでしょう。
これを嬉しがっている時の表現として放置せずに、親がリビングで黒子として上手に反射を止めてあげて、
手はお膝にして椅子に座らせ続けることが、嬉しい気持ちと体の分化を促し、目と体の分化も促します。
30分くらいは椅子に座っていられる体に育てていきましょう。
中略
6静かに待てる体にするために
外出マナーを教えるには、歩行トレーニング、着席注視持続トレーニングが基礎にあります。見るものがあれば、30分くらいは座っていられるようになったら、何もない状況でも、体を止めて少し待っていられるように練習をしましょう。
コロロでは「行動トレーニング」と呼んでいますが、正座、イス着席、立位などの、一定の姿勢を保持する練習です。
立ち位置、座り位置をわかりやすくし、最初は10秒から、徐々に時間を延ばし、5分、10分、できれば20分くらいは一定の姿勢を保っていられるように練習します。
これができるようになったら、口の常同行動(独語)を止める練習を始めましょう。
独語の多い子は上下の唇を閉じ続けることができません。
その場合は、コインやカードを口唇にはさむ練習をします。
口唇を閉じ続けられる体を作っていくのです。10ヵウントから少しずつ伸ばしていきます。

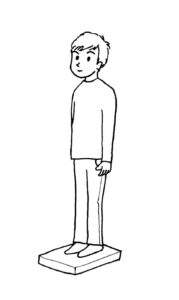
正座 立位
飛行機に乗って旅行したり、映画を見たりなど、静かに過ごせるようになることは子どもの生活の幅を広げます。
子どもが自分で体をコントロールできるようにするための行動トレーニングが、
ゆくゆくはマナーを身につける身体をつくっていくということがおわかりいただけたら幸いです。
この記事をご紹介したのは…
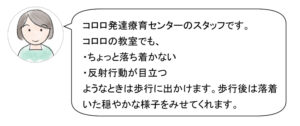
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




