『どうしたらうまくいく?集団指導Q&A』の記事をご紹介します。
Q1
放課後等デイサービスの職員です。集団活動中にみんなのことは見ているのですが、
部屋の隅に座って動き出せない子がいます。
どのように活動に誘えば良いでしょうか。
A1
集団活動ができないという理由でコロロの教室を訪れるお子さんが大勢います。
そんなお子さんもコロロでは、「集団が個に合わせる」ことで早期に集団参加ができるようになります。
実例をもとに、対応を紹介します。
初めて杉並教室に来たC君は階段に座り、その場から動くことができませんでした。
リズム体操をしている集団を見てはいるものの、そこから動かず、促そうものなら身体が固まり、
顔がうつむいてしまい参加できそうにありません。
そこで、みんなでC君を囲むように階段に座り、集会を行いました。
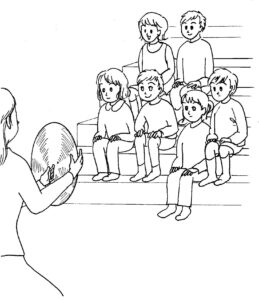
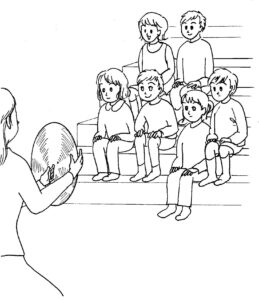
階段や玄関などどんな場所であっても、集団に入れない子がいる場所に合わせて、集団を形成することがポイントです。
その際は、コンパクトな集団形成を意識しました。
バラバラに座っているよりも、一か所に固まって座っているほうが
「自分は他の人と同じようにすればいいんだ」と視覚的にわかりやすいのです。
好きな電車の教材が出てきたことをきっかけに、C君が皆と一緒に集会を見始めました。
15分位落ち着いて集会を見た後、みんなで一斉に立ち上がり二列行進でリズム体操を始めたところ、
C君の体がすんなりと動きました。
C君の体がすんなりと動きました。
リズム体操に参加できたC君でしたが、座るときは階段の方へ戻ってしまいました。
そんな時は、またみんなで階段に座って集会や作業を行いました。
トイレに行く時も、食事をする時も、とにかくC君に合わせて他の子どもたちも一緒に移動しました。
このように「気づいたらみんなと一緒に活動していた」状況を作り続けたところ、
一日で階段以外でも集団が座っている場所に合わせて、自ら移動して座ることができるようになりました。
集団がC君に合わせて協力することで、C君の集団参加のきっかけになったのです。
①集団に入れない子が、その時一番参加しやすいプログラム・配置に切りかえること
(C君の場合は“階段で集会”)・・・予定していたスケジュールに縛られないことが大切です。
②その子が集団の中で目的行動がとれるように、集団の形のまま次のプログラムに移ること
コロロでは、困っている子がもし室内に入れないのであれば、外で受け入れて、他の子どもたちと一緒に外に歩行に出かけます。
また、ちょっとした待ち時間があると泣いてしまう子がいれば、
集会をしながらトイレ誘導を行ったり、靴を履く時間を削減するため、
室内でみんな靴を履いてリズム体操を行い、そのまま玄関を出て歩行に行ったりします。
その子に合わせて集団を動かすので、大幅にスケジュールを変更することもあります。
このように、集団に入れない子ができること・できる場所に合わせて、
活動内容・場所を柔軟に変えてみてはいかがでしょうか。
この記事をご紹介したのは…
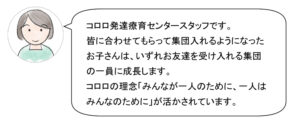
活動内容・場所を柔軟に変えてみてはいかがでしょうか。
この記事をご紹介したのは…
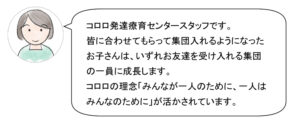
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




