『タイプ別 高機能自閉症児の適応力と認知力を伸ばす学習指導』の記事をご紹介します。
コロロでは、集団でリズム運動や集会、歩行をすることで身体の発達や適応力を上げる集団療法と、
文字を書いていくことで発語を促したり、概念学習を行うことで社会適応力を上げる学習療育を行っています。
お話がよくできる高機能自閉症のお子さんと学習をしていると
「この子の頭の中に他者の存在はどれくらいあるのだろう?」
「物事の考え方のベースはどこにあるのだろう?」と知りたくなる時があります。
例えば、話ができるにも関わらず「人を叩く」という行為があり、それが繰り返され問題行動となって相談に来られた時です。
そんな時、子どもに次のような質問をしてみます。
質問1「お友達を叩くのは良いことですか?」
質問2「どうして叩いてはいけないのですか?」
質問1に対してはどの子も「ダメ」と答えますが、質問2に対する回答は大体四パターンに分かれます。
【タイプ別!四つの反応パターン】
一つめの回答パターンは、理由がわからなくて黙ってしまう子、「わかりません」という子、首を傾げる子たちです。
「なんとなく」と答えた子もいます。
これは、「叩いた」ことが無意識だったり、あるいは思い出せない(イメージ記憶がない)状態の反応です。→ Aタイプ
二つめの回答パターンは、「先生に怒られるから」「ママに怒られるから」「友達をなくすから」等、
自分を中心に物事を考えて、まだ相手の立場に立った見方をしていない自己中心的認知の場合です。→ Bタイプ
三つめは、「お友達がいやだから」「相手がいたいから」「お友達が傷つくから」等、相手の立場に立ったことばが言える、
もしくは、誰かに教えられてこの答えになることもあります。
すべて相手の立場の見方ができるわけではないので、状況により自己中心的になります(自己中心的思考I)。
ただ、この回答をする子どもは「叩く」という行為自体はしないことが多いです。→ Cタイプ
四つめは、「暴力だから」「犯罪だから」「入院費用を払わないといけないから」等、相手の立場で物事を考えるのではなく、
「ルール」の下で考える思考パターン(自己中心的思考I)の子どもです。→ Dタイプ
【いくら言葉で説明しても問題行動を繰り返すのはなぜ?】
お友達を「叩く」子どもに対して、学校ではどのように対応しているかというと、
叩かれた子どもの気持ちを説明し、謝らせ、もう二度と叩かないように約束させるのが一般的です。
けれども、また叩きを繰り返すか、もしくは、叱られたことに反発してしまい、反省させられないのが現状のようです。
高機能自閉症児は、ただやみくもに相手の痛みを説明していくだけでは良くなりません。それはなぜでしょうか?
その理由は、そもそも対人認知が弱いため、他人の感情や情緒がわからず、相手の立場に立った思考ができないからです。
いくら相手の気持ちを説明しても、全くイメージできないので抑止に繋がっていきません。
では、高機能自閉症児にとって、どういった対応や学習が、適応力と認知力を伸ばすのに効果的でしょうか?
A~Dタイプの回答別にお伝えしたいと思います。
【タイプ別学習方法】
Aタイプの場合

まず、Aタイプの場合です。
この子ども達は、言葉の「叩く」とその行為はマッチングしていますが、それと自分の行動がリンクしません。
意識レベルがグンと下がった時のささいな接触や、もしくは、その時聞こえた音が不快刺となって、
側にいた人を叩いてしまうというようなことが多いので、後から聞いても覚えていません。
意識レベルが低いので、叩いたことをその場で叱ると、更にエスカレートし、暴言や暴力になることもあります。
この認知レベルの子どもは、お話はできても、生活は常にパターンで動いています。
例えば、本人がエアコンをつけたときに「どうしてエアコンをつけたの?」と聞いても、理由は言えません。
言語で考えず、パターンで生活している子どもは、自分の行動の理由を言葉で説明できないのです。
言語で考えず、パターンで生活している子どもは、自分の行動の理由を言葉で説明できないのです。
Aタイプの子どもの叩く行為をなくしていくためには、叩いた後に叱っても反発ばかり増えてしまうことが予想されるため、
まずは叩かせない環境設定が必要になります。
並行して、学習課題では、自分がパターンで行っている日常の行動を一つ一つ言語化させて意識化させていくことが必要です。
例えば、「行動の順番」という課題です。
トイレ、お風呂等、ある目的に向かってする事の行動を順番に細かく言語化させます。
もし、イメージを言語化できなければ、実際に子どもが行動している側で一つ一つ言語化させ、
その記憶がはっきりしているうちに、もう一度机上で振り返り、順番を書かせます。
その記憶がはっきりしているうちに、もう一度机上で振り返り、順番を書かせます。
これが記憶の強化に繋がっていきます。
Aタイプのお子さんはイメージが全くないわけではないのですが、言語化しないと、強烈なこと以外は消えていきます。
行動の言語化を繰り返すことが、その先のセルフコントロールに結びついていきます。
その他の課題としては、因果関係、時系列の絵の順番と言語化、物事の順番、問題解決学習などがあります
(詳しくは「自閉症児のことばの学習~話せるようになってからの概念学習(コロロ発達療育センター)」を参照してください)。
無意識的な行動が多いAタイプは、問題行動を引き起こさない環境設定と、自分の行動の意識化のための言語学習を!
本紙『発達プログラム157号』にて、Bタイプ~Dタイプの説明をしています。
ほか、「こんな子にこんな学習」では以下のようなタイプ別学習法も紹介しています。
①なんでも払い落としてしまい、学習にならないA君
②発語のない子の言葉を引き出す学習
③会話にならない子に、言葉のキャッチボールを教える学習
④問題の解き方にバリエーションを持たせて
⑤常同行動をせずに持続できる力をつけるための学習
⑥重度の子に、考える力を育てるための学習
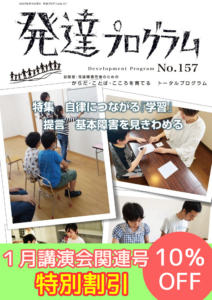
②発語のない子の言葉を引き出す学習
③会話にならない子に、言葉のキャッチボールを教える学習
④問題の解き方にバリエーションを持たせて
⑤常同行動をせずに持続できる力をつけるための学習
⑥重度の子に、考える力を育てるための学習
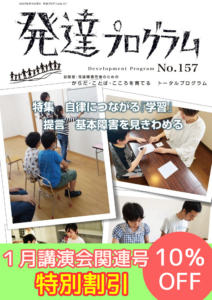
また、本紙は1月26日(日)の講演会関連号として特別価格にて販売しております。
講演会情報も併せてご覧ください。
この記事をご紹介したのは…
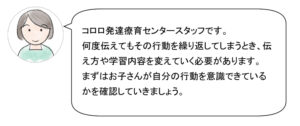
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎






