発達プログラム150号早期療育―身体・ことば・気持ち・育ちの基礎づくり―より
「はい!お答えします①お気に入りのおもちゃを手放せません」の記事をご紹介します。
Qご質問
5歳になる年中の息子です。
現在保育園へ通っています。
以前より、テレビを見る時や寝室へ移動する時、食事の時に、必ずおもちゃを一つ手に持っていることが目につくようになっていました。
最近は近所の祖母宅やスーパーへ行く時にも持って出かけます。
ある日、登園する時に持っていこうとしたので、「保育園には持っていかないよ」と取り上げようとしたら、
泣いて叫んで抵抗したものの、何とか保育園へ連れて行きました。
保育園の先生から、「本当はいけないのですが、心が落ち着くならば園に持ってきてもいいですよ」と許可を頂いたので、
それからはおもちゃを持って登園しています。
ところが最近、他の園児が「〇〇くんずるいよ!」と先生に訴えているのを見てしまいました。
このまま息子が園におもちゃを持っていき続けることは良くないとは思っていますが、あんなに抵抗されると、
ただ取り上げることが良いことなのかと悩んでいます。
ただ取り上げることが良いことなのかと悩んでいます。
A解答
先生から許可をもらっていても、園のルール通り、おもちゃは持ち込まないのが良いと思います。
今後社会のルールに合わせて行動しなくてはならないことがたくさん出てきます。
ルールに合わせて行動することが常であることを幼児期から習慣化することは大切です。
とは言っても、お母様がおっしゃる通り、ただおもちゃを取り上げるという事はお子様にとっても不快この上なく、
よりおもちゃへの固着を強めてしまいます。
だからと言って「保育園へ持っていってはいけないルールで、お友達も持ってこないから・・・」と長々説得したところで、
理解できず自らおもちゃを手放すことは難しいでしょう。
祖母宅は持っていってもいいけれど、保育園はダメという違いが分かりづらい今の段階では、
「おもちゃを持ち歩かないでいられた」という、新しいパターンを作ることが先決です。
保育園にだけでなく、家庭内でも持ち歩く時間が増えているようですので、まずはその点から改善してゆくとよいでしょう。
家庭内の環境設定をしましょう
おもちゃは、遊びやすいようにと、家の中でも目につきやすい所や手の届きやすい所にあるのではないでしょうか。
目についたら手に取りたくなるものです。
おもちゃで遊ぶ時間以外、目につかないよう扉の中に片付けるなどしてすぐには手に持つことが出来ない環境を作りましょう。
手に持つ時間を短くしてゆきましょう
なぜ手に握り持ち歩くかというと、握り反射の残存と感覚刺激を求めることが原因です。
手の平に一定の感覚を入れている時間が長くなれば長くなるほど、その感覚がなくなった時の不快が増します。
また感覚刺激は快刺激なので「もっともっと」と欲求が強くなってゆきます。
おもちゃを持ち歩くこだわりをそのままにした結果、ある成人男性は、決まった人形を9個顔の周りにビッチリ並べないと眠れず、
家の中でもそれを持ち歩き、外出先には2個持っていくと決めています。
「大きくなったらやめるだろう。おもちゃに触味がある今だけの行動だろう。」と考えがちですが、
大きくなったから無くなるということはほとんどありません。
反対に手放す事が出来なくなってしまう事の方が多いのです。
感覚刺殿に浸っている間は大脳新皮質が働いていないため、他者からの問いかけにも反応が悪くなります。
感覚刺激に浸る時間を少しでも短くすることが必要です。
テレビを見る時はかごに入れて自分の隣に置いておく。
ご飯を食べる時もかごに入れて床に置いておく。
お出かけする時も袋や鞄に一旦入れることが出来るならばその方が良いでしょう。
他の物を介して直接握る時間を減らすようにしましょう。
さりげなくフェイドアウト
手に握ってしまったものをかごに入れるようするには、一旦手から離さないといけませんが、一度握ったものはなかなか手放さないはずです。
無理に取り上げれば大泣きになるでしょうから、手放す状況を作りましょう。
食事前に手を洗うよう促し手を洗う時にかごに入れるよう指示します。
手を洗っている間にかごごと視界から遠ざけます。
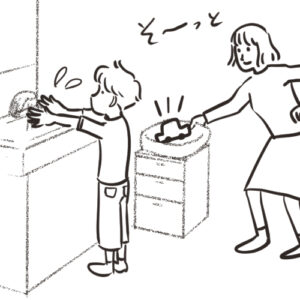
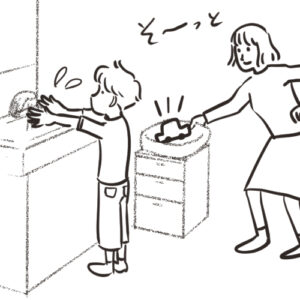
手洗いが終わり手を拭いたら、間髪入れずに手を繋ぎ食卓まで誘導し食事にしましょう。
外出先で歩いている時も、おもちゃを握っていない方の手をつなぎ歩きましょう。
つなぐ手を交換する時必ず、おもちゃ持ち替えようとするはずです。
その時にさりげなくおもちゃを引き取ります。
さりげなく、気付いたら持っていなかったという状況をつくりましょう。
生活の中でおもちゃを持つ時間が減って来ると持っていない時の不快は減っていき、持たないことが出来るようになってゆきます。
迷惑行為かそうでないかが問題ではない
こだわり行動の相談を受ける時に私が親御さんに確認する事は、「それ以外のこだわり行動は何かありませんか?」ということです。
こだわり行動は皆さん1つではありません。
こだわり行動で困っているというお子様は、生活の中に様々なマイルールと呼ばれるこだわりがあります。
車の席、食卓の席、靴の履き方、洋服の種類等、それは一人でしている分には誰にも迷惑がかからないものです。
いつも決まった自分のパターンで動いているところに、突然「それは他の人に迷惑だからやめなさい」と言われても
応じる事が出来ないのは当たり前の話です。
『いつも同じ時間帯、同じ場所、同じ物、同じことをする』、これは「こだわり』です。
困った行動になっていなくてもこだわり行動のパターンをこまめに変えてゆくことが、子どもの臨機応変な対応力を養うことになり、
結果、人に迷惑をかけるようなこだわりも回避することが出来るようになるのです。
この記事をご紹介したのは…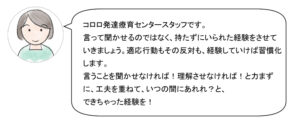
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




