〈コラム〉特定の場面・人に対して同じことばをくりかえしまう…これも反応格差現象です
発達プログラム124号「ことばQ&A」より
先日、あるお母様から次のような相談をうけました。
原因① マイペースなことば
原因② 特定の場面・人に対して同じことばを繰り返す
原因③ 自分のことばが「刺激」となって、激しい思い込みになる
②場面回避と複数記憶行動
③快・不快と実際行動の区別
最後に、ことばによらない「パターン言語」対策をご紹介します。
【誰とでもできる!を目指す!】 反応格差を知る2冊セット ”81号146号”
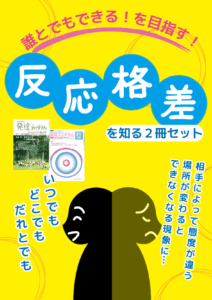
お子さんのまちまちな反応に驚くことはありませんか?
例えば、
学校ではできるが家ではできない。
お母さんとはできるが他の人とはできない。
ここではできる、でもあそこではできない。
これらの現象をコロロでは「反応格差」と呼び、療育的視点で捉えプログラムをたてて対応をしています。
高機能自閉症のパターン言語 の記事をご紹介します。
先日、あるお母様から次のような相談をうけました。
「息子のMは21歳で、高機能自閉症です。中学までは普通級に通い、特別支援学校高等部を卒業して、一般就労しましたが、長続きせず、現在は地域の通所施設に通っています。ところが、最近落ち着いて通うことが難しくなってきました。というのは、相性の悪い利用者の方がいるようで、『〇〇は注意しても何度も悪いことをしている』、『スタッフも〇〇を叱ってくれない』、『〇〇むかつく』と同じ方の名前を繰り返し、家でもずっとイライラしているのです。施設の方に確認すると、〇〇さんの近くをうろうろしたり、じっと睨んで、こっそり叩いたりするそうです。それをスタッフの方が注意すると、逆ギレ状態で食ってかかるので対応に困っていると、仰っていました。どうしたらこの状態を打開できるのでしょうか」。
お母様のお話から、Mさんのことばが「パターン言語」であるために、様々な問題を引き起こしていることがわかります。
「相性」の問題ではないのです。
「パターン言語」とはどのようなものでしょうか。その特性に照らして、原因と対応法を考えてみましょう。
原因① マイペースなことば
Mさんの言葉は「〇〇が悪い」「〇〇むかつく」と一方的にまくし立てるばかりで、コミュニケーション(やりとり)になっていません。
相手・周囲に合わせられないマイペースなことばなのです。
その原因は、共感能力を司る脳の部位である「扁桃体」の機能が弱いためと言われています。
周囲が説明しても納得しないことが多く、だからと言って無視すると、かえってイライラを助長しがちです。
この場合、「よく話を聞いてあげる」という受容と共感的対応は、ほとんど効果がありません。
説明するほどにかえってそのことに注意が集中して、余計に執着をエスカレートさせる危険があります。
原因② 特定の場面・人に対して同じことばを繰り返す
それは「特定の場面・人」という「刺激」に対して、「同じことばを繰り返す」という「反応」を示す条件反射なのです。
条件反射ですから、〇〇さんを見ると、「〇〇むかつく」と言わずにはいられない、自分でことばを止められない、コントロール不能状態になっているのです。
人間の脳は繰り返すことによって物事ができるようになりますが、一方で考えなくなる性質も持っています(考えなくてもできるようになる)。
人間の脳は繰り返すことによって物事ができるようになりますが、一方で考えなくなる性質も持っています(考えなくてもできるようになる)。
考えていれば同じことばを繰り返すことは無いものです。
よって、ことばの意味・内容をそれほど考えて言っているわけではないので、私たちが思うほどストレスにはなっていないものです。
原因③ 自分のことばが「刺激」となって、激しい思い込みになる
「〇〇が悪い」「〇〇むかつく」といったことばを繰り返すことにより、本人の不快反応がどんどん強化されていきます。
自分にとっての「不快→悪いこと↓〇〇は悪いやつ」となり、相手に対して、暴力的な攻撃行動に発展してしまいます。
この場合、本人は、自分の考えは「正しい」と思い込んでいます。
このあたりの本人の思考パターンを正確に把握し、方向づけを誤らないようにすることが高機能自閉症者への対応における難しい点です。
このことは、好きなことについても同様です。
快も不快もパターン(思い込み)になってはいけないのです。
【対応法】
①聞いてから行動する
「他人の話を黙って聞く」、「尋ねられたら答える」、「聞いてから動く」というコミュニケーションの基本から練習し直しましょう。
その際、Mさんの「マイペースなことば」には「ああそう」くらいで上手く受け流して、できるだけ別の話題・活動に切り替えるよう努力してください。
Mさんのまくし立てることばに、まともにとり合わないことです。
「ゴミを捨てて来て下さい」→「はい、わかりました」→実行、という端的なやりとりからユアペースを徹底しましょう。
②場面回避と複数記憶行動
「相性の悪い〇〇さんを見ると・・・」という条件反射ですから、ひとまず〇〇さんが視界に入らないような場面回避を、通所先でお願いできると良いです。
加えて家庭では、一対一の条件反射を乗り越えるべく「同時に二つ以上の役割行動をさせる」ことを励行しましょう。
例えば、「台所からミカンを3個持って、応接間の机の上に置いてから、お父さんに新聞を届けなさい」といった指示を出します。
それは「次の行動の予定を頭の中に一時記憶しながら、今の行動に取り組む」ことになり、一対一の条件反射を打破する練習になります。
③快・不快と実際行動の区別
例えば「△△を欲しいけれどお金が無いから(我慢する)」、「電車が見たいけれど時間が無いので(すぐ帰る)」といった文章題に取り組み、自分の不快感と実際の自分の行動とを区別させます。
自分の不快感を制御し、正しい善悪判断を導き、実際の行動につなげるのです。
この時、自分のことば(音刺激)によって、より強化されていく傾向があるため、黙って取り組むよう留意して下さい(沈黙思考の境地)。合わせて快感情を意識して言語化することも大切です。
例えば、
「登山で汗びっしょりになりました→(頑張ったので、すがすがしい気持ちです)」
「登山で汗びっしょりになりました→(頑張ったので、すがすがしい気持ちです)」
「マラソンでやっとゴールインしました→(気分はさわやかです)」といった文章題や問答を練習します。
そして、快感情のことばを使うよう助長しながら、日記をつけさせます。
「今日、美しい夕焼け空を見て、僕はおだやかな気分になりました」、「毎日、家族に助けてもらい、とても感謝しています」というレベルの文章も書かせたいものです。
本人が見えていない・気づいていない部分を言語化させることで、パターン言語を乗り越えさせるのです。
助言されながらも自分で書くことは、快感情と正しい判断・行動を結びつける上で、とても効果的です。
ところが、今の教育福祉界では「本人が公と言うから、本人の意思を尊重してあげねば」という風潮があります。
ですが、それでは本人の快・不快感が、そのまま思い込みや攻撃行動につながってしまうので留意が必要です。
日記も、良く書けるようになったからといって、本人の思うままにマイペースに書かせてしまわないように、いつのまにか「不快感し苦しい、嫌だ、〇〇は許せない」といった文章になってしまわないよう、お母様のチェックは怠らないようにしてください。
最後に、ことばによらない「パターン言語」対策をご紹介します。

高機能タイプの方でも、暑い日も寒い日も2時間以上の長時間歩行を続けることによって、ガラリと状態がよくなった、という話をよく聞きます。
理由は定かでありませんが、持続歩行により心身のバランスを整えるセロトニン神経が活性化するのでは、とも言われています。
従って、ことばを介在せず2時間以上みっちり歩き続ける、という行動のリズムを整えるべく体を使った持続運動は、大変効果があります。
歩行と併用して、例えば、写経の如くひたすら漢字や文章を模写させる持続課題を提示し、暇な空白時間が生じないよう、一方的な言動が始まらない環境を設定するとより良いです。
親御さんの中には「ここまでことばが育ってきた我が子に、今さら歩行や模写なんて…」と思われる方もいるかもしれません。
ですが、「一般就労したから歩行や学習はもう卒業」と決めたものの、数年後、状態が悪化し、家庭生活が困難となり、数ヶ月間の施設入所(ショートステイ)で立て直しを図る例が沢山あります。
反対に「ここまでことばが育ってきても、まだ発達途上。我が子は一生基本的な療育が必要」と歩行・学習をかさない成年期ケースの状態は概ね良好です。
こうした親御さんの意識は成年期の我が子の状態を大きく左右するものです。
この記事をご紹介したのは…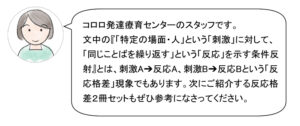
【誰とでもできる!を目指す!】 反応格差を知る2冊セット ”81号146号”
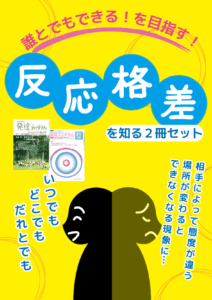
お子さんのまちまちな反応に驚くことはありませんか?
例えば、
学校ではできるが家ではできない。
お母さんとはできるが他の人とはできない。
ここではできる、でもあそこではできない。
これらの現象をコロロでは「反応格差」と呼び、療育的視点で捉えプログラムをたてて対応をしています。
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




