適応力を高める生活動作の教え方 の記事をご紹介します
●生活動作の習得で安心しない
生活動作を習得していくことは、自分一人でできることが増えることですからそのこと自体が「適応力が身についた」と思われことが多いと思います。
すこし私たちの日常を考えてみたいと思います。
たとえば約束に遅刻しそうなときは身支度を急いでおこなったり、「これはまあ、いいか」と省いたりしていますよね。
反対に、時間に余裕がある時は掃除を丁象にしたり、テレビを見ながらゆっくりと・・・なんていうこともあると思います。
私たちは生活動作のスキルをその状況に応じて変化させていきます。
「状況に合わせて行動を柔戦に変化させていく」ことが自然と無理なくできるようになっています。
では発達障害がある方々の場合はどうでしょうか。
以前に、発達プログラムー29号「ケアホーム隣家火災と療育の重要性」にて、火災という非常時の利用者の皆さんの様子を紹介しました。
みなさん、非常に落ち着いて避難が出来たのですが、それでもやはり「入浴途中に入浴を切り上げて避難するのにすこし抵抗感を示した」ということでした。
コロロの教室に通う保護者の方からも、
「風邪を引いたのでお風呂をなしにしたら怒ってしまった」
「急用が出来て出かけたかったが、日課の洗濯物干しが終わるまで出かけられなかった」
「ヘルパーさんが靴を履くときに手伝ってくれたが、それが気に入らずに何度も何度もやり直して動けなかった」
というエピソードから、中には「燃えるごみ、燃えないごみの分別を間違えたら怒ってしまった」
「10月1日の衣替えより前に長袖を着ることが出来ない」なんていうエピソードまで幅広く?相談が寄せられます。
「風邪を引いたのでお風呂をなしにしたら怒ってしまった」
「急用が出来て出かけたかったが、日課の洗濯物干しが終わるまで出かけられなかった」
「ヘルパーさんが靴を履くときに手伝ってくれたが、それが気に入らずに何度も何度もやり直して動けなかった」
というエピソードから、中には「燃えるごみ、燃えないごみの分別を間違えたら怒ってしまった」
「10月1日の衣替えより前に長袖を着ることが出来ない」なんていうエピソードまで幅広く?相談が寄せられます。
読者の皆さんは、思い当たることがありませんか?
●生活動作を教えながら適応力のトレーニングも行う
身の回りのことが出来るようになると生活はうんと楽になります。
本人の自信にもつながります。
しかし、生活動作のスキル向上だけが生活を豊かにしていくわけではないのです。
生活動作を教えることと同時に、「変化する状況(場所・時間・人など)に合わせて生活動作を変えていく」ということを教えていく必要があります。
ここではその指導方法について考えます。
①生活動作のパターンを教える
生活動作の教え方はこれまで見てきたとおりです※。お子さんに合わせての目標設定とそれに向かった工夫が必要です。
(※発達プログラム131号掲載の内容です)
②生活動作のパターンを崩す
「パターンを教える」までで終わりにせず、それを変化させていくことにも取り組みましょう。この「崩し方」が適応力を高めるコツです。
パターン崩し・その1 場所を変える
靴の着脱がお家でもできるようになったら学校でもできる、
病院の待合室で下駄箱から出して着脱できる、
道路を歩いている途中に脱げてしまったけれど履きなおすことができるなどなど、
「靴の着脱」場面は多くの場面で起こります。
病院の待合室で下駄箱から出して着脱できる、
道路を歩いている途中に脱げてしまったけれど履きなおすことができるなどなど、
「靴の着脱」場面は多くの場面で起こります。
ときには、靴のまま入るところだってあります。
あらゆる場面を想定して、「靴の着脱場面」のパターンを増やしましょう。
パターン崩し・その2 人物を変える
お母さん、担任の先生が毎日関わる人物ですから教える機会が多くなります。
すると、「お母さん(または〇〇先生)とはできるけど…・・・・」、ほかの人になるとほとんどできない、なんていう現象が起きてきます。
良いパターンが身についたところで、お父さんと、兄弟と、ヘルパーさんとさせてみましょう。
またお母さんは「口数の多い人」「せわしない人」などなど「こういう人いるいる!!」というタイプを演じてみるのも一つです。
パターン崩し・その3 手順を変える
洋服を一人で着られるようになった・・・・「やっぱり寒いから下着にこれ着ときなさい」とか「それを着る前に、お薬飲んでおこう」という手順の追加・変更はよくあることです。
さらには「時間がないから、今日はお母さんがやっちゃうね!」なんて大幅カットはなおのこと。
「一人で全部する」というパターンだけがついてしまうと、いざ!という時に思わぬ反発を招きます。
なので、お母さんや先生に余裕があるときに「いざ!」の練習をしておいてください。
「自分で思った通りに出来ないこともある」ということまで教えておくのです。
パターン崩し・その4 教える側のバリエーションを変える
上記のパターン崩しになれてくると、子どもにとってはそれもパターンになります。
ある程度「適応力がついたな」と感じたら、ここには載っていないような新しい「我が家ならでは!」というパターン崩しを考えてみてください。
・日課にまでなったお手伝い…・・・今日は何もしなくていいわよ
・お風呂上がりの着替え、一人でできるけれど…・・・・・今日はお母さんが着せます!
・帰毛後の荷解き、正確にできてきた・・・・今日は学校に忘れ物をしてきたということにしよう!
などなど。こういうことは、ここに書くよりも生活を共にしている時間の長いお母さんや先生が考えるほうがよいでしょう。
お母さんや先生の「療育的な自由な発想」をフルに発揮させてみましょう。
ただし、いくら幅広いパターンをといっても「周囲の人から歓迎されないこと」や「マナー違反になりそうなこと」はやめましょう。
あくまで「正しいパターンを増やす」ということが大切です。
●せっかくついた良いパターン・・・・•・本当に崩すの?
いつまでもお父さん、お母さんの目の届くところで生活を送っていくことが出来るわけではありません。
残念ながら、お父さんお母さんがいない人生の時間のほうが長いのです。
その中で色々なことがあり、人と出会います。
障害に理解を示し適切な対応をしてくれる人、障害は知っているけど対応の下手な人、まったく無関心な人、世話好きでなんでも手伝ってくれる人・・・様々です。
良い支援者と巡り合えるほうが稀だと思っていて良いくらいです。
でもそうした環境に置かれたときに、介助が下手な人を殴ってしまったり、世話好きな人の手助けを断ってしまったりして「神経質で対応の難しい人ね」とレッテルを張られてしまうと、どうでしょうか。
結局は本人が不幸になります。
自分でも大体のことはできるけど、人からの手助けをいつでも「ありがとうございます」と素直に応じることもできるというほうが、本人も周りの人も幸せだと思います。
自分でも大体のことはできるけど、人からの手助けをいつでも「ありがとうございます」と素直に応じることもできるというほうが、本人も周りの人も幸せだと思います。
「状況に応じて自分でもできる、変更もできる、人の介助も受けられる」ということを教えておいてあげることが今支援に関わっている私たちにできる、未来への支援になるのだと思います。
この記事をご紹介したのは…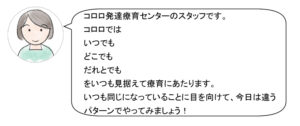
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




