発達プログラム145号―自立のための身体づくり― すべてにつながる「体幹」より
教えよう!一人時間の過ごし方 車内での過ごし方編
の記事をご紹介します。
通学・通院・お買い物・レジャー等生活をする上で、乗り物に乗って移動することはきっても切り離すことが出来ません。
公共機関や自家用車移動、移動手段はたくさんありますが、みなさんはどのような手段をお使いでしょうか?
車移動は非常に便利です。最近はカーナビゲーションや、スマートフォンンの道案内システムがあるためより便利になりました。
しかし、車移動は公共機関よりも車内での過ごし方が難しいというお声も頂きます。
ご両親そろっての移動ならば楽にできても、大人が一人でお子様をみながら運転するのはとても難しいものです。
《どうしたら上手くいく?車移動》
二人のお子さんの、車内での様子をご紹介します。
Aさんは車の扉が開くと、そそくさとワンボックスの一番後ろの端の席に乗り込みます。
そして、お母さんにいつものヘッドホンを要求し、お気に入りの曲をかけてもらいます。
そして移動中ひとしきり音楽を聴き続けます。かと思うと、急に店名を言い出し、そこに行きたいと要求します。
要求を受け入れないと大声で叫び続けるため、結局お店によることになります。
目的地に到着しても、なかなか降車出来ません。
好きな場所だと降りてきますが、本人にとって不快な場所だと抵抗し降りようとしません。
Bさんはお母様が決めた場所にのせ、シートベルトを着用させます。
車内では、車内のオーディオを使って曲をかけます。
選曲は毎回変えています。時には曲を飛ばすこともありますし、途中で次の曲に変えることもあります。
曲をかけない時には、しりとりをしたり、車窓から見えるものを題材に質問もします。
そうこうしているうちに目的地に到着です。
たとえ本人にとって好きな場所ではなくてもお母様の指示でスムーズに降車します。
AさんとBさんは、車内で同じように音楽をきいています。
音楽を聴いて過ごすことは有効です。
では、同じ行為をしているのにも関わらず降車時の状態が違うのはなぜでしょうか?二人の違いを見てみましょう。
〇乗り方
Aさん:自ら乗り込む
Bさん:指示されたところに乗る
〇音楽の聞き方
Aさん:自ら操作。
Bさん:再生、停止、スキップボタンはお母様が操作。選曲もお母様がする。
〇その他
Aさん:一方的な要求のみ
Bさん:時々やりとりをする
Bさんは車の乗車時から降車時までお母様が介入しています。
Aさんは終始自分一人の世界です。
同じ行動をしていても、他者からの介入があることで意識レベルを一定に保つことができ、問題行動の出現をおさえることができるのです。
《移動には練習が必要》
Bさんが始めからお母様の介入を受け入れられたわけではありません。
座る位置や、順番等もこだわりになりやすいため、お母様は普段からいろいろな場面でパターン化しないよう変化をあたえるよう心がけています。
移動もお母様が車を運転してしまうと、子供の状態の変化に素早く対応が出来ないため、いつでも対応が出来る電車で練習したそうです。
電車では、乗車中イライラしだしたら、次の停車駅で途中下車しお母様の手から1つずつ好きなお菓子を口に運び、
呼吸が整ってきたところで再度乗車します。
このような事を何度も繰り返し目的地に向かっていました。
音楽が好きだったので、音楽をイヤホンで聴かせるようにすると、静かに乗車している時間が延びてきました。
その時も一人で機器操作してしまうと、降車時に「降りますよ」の指示に反応が悪くなってしまうため、
イヤホンの片方はお母様、片方をお子様が装着し、機器はお母様が操作しました。
他の乗客の方に迷惑がかからない音量調整も心がけました。
曲の途中で終わりにすることは、本人にとって不快です。
しかし、同じ曲を聴いているため、曲の終わりで一旦終了にしておき、次の行動に移りやすくしておくこともできました。
始めは本人への負荷を調整しながら、ルールを守って静かに乗車出来た経験値を積んでいきました。
電車で2時間近い移動が可能になると、お母様が運転する車での移動もスムーズになりました。
電車での移動は静かに出来るようになってからと考えがちですが、電車で移動すること自体が療育課題として意義があります。
車と違い、常に足を使いますし、大人が隣につき手つなぎ歩行が出来ます。
階段昇降もあります。揺れる車内で体幹を保ち立っていなくてはなりません。
車では大人側も「まあいいか」というゆるみも出ますが、電車では他者からの目があるため気も引き締まり、それが子供にもよい影響を及ぼします。
乗れれば良い・移動できれば良いというのではなく、どう乗れるか・同乗する方に合わせて移動できるかが重要です。
乗り物に乗り続けることも、日々の練習が必要だという視点で、毎日の歩行や行動トレーニングに臨んでみてください。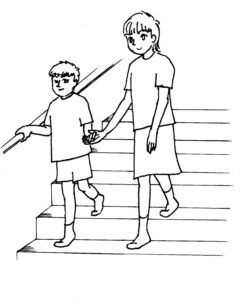

この記事をご紹介したのは…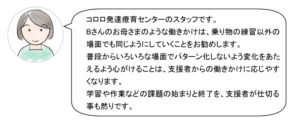
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




