発達プログラム No.151 「一冊まるごと問題行動Q&A」<第三章>多動・寡動より
飛び出しを減らすための「手つなぎ歩行」に向けてのステップの記事をご紹介します。
Q
4歳自閉症の息子を持つ母親です。
息子(Y)はエアコンの室外機に興味があり、道を歩いていると室外機に向かって走り出してしまいます。
危ないので手を繋いで歩こうとしますが、私の手を素早く振りほどいてしまい止められません。
手を離されないように力を入れて手を握ると、今度は大声で泣いて寝そべってその場を動けなくなってしまいます。
「どうしても見たいんだ!」と訴えているようです。
どのようにトレーニングをしたら良いでしょうか。
A.
Y君はこだわりの強いタイプのお子さんのようですね。
外に出てもこだわりのものが目に入っては飛び出してしまう、このような状態では交通事故のリスクもありますし、本人やご家族の社会生活の幅を狭めてしまうことになります。
こだわりが強く歩行が難しいお子さんと歩くにはコツがありますので、できるところから段階的に始めていきましょう。
①お母さんの指示に応じてできることを増やす
外を歩いている時だけでなく、普段から人からの指示や声かけに対して応じることはできているでしょうか。
それが難しければ、まずは何でも良いので、他の人のペースでできることを増やしてあげる必要があります。
よい状態で外へ行くことが難しい場合、まずは室内でできることを増やしていくことをお薦めします。
例えば、簡単な課題を座って取り組むことができるお子さんであれば、シール貼りや物入れといった作業課題や自習の時間を一日の活動の中に取り入れましょう。
ただし本人のやりたい時だけ、好き勝手に遊びながら行うのでは意味がありません。
お母さんが対面し、教材一つずつ手渡ししてお母さんのペースで行いましょう。
このように人の介助を受けられる、ペースを合わせられる時が手をつなぐチャンスです。
例えば、ごみ捨てや片付け、トイレやお風呂へ行くときなど、室内でのちょっとした移動の中で手をつなぐ練習をしていきましょう。
②刺湯の少ないところを歩く
街中を歩いていると室外機はいたるところにあります。
特にご自宅の周りはどこに室外機があるかを熟知しており、飛び出しや制止した際の癇癪が起こりやすい、ということはありませんか?
発達障害のお子さんは、同じ刺激による行動(反応)を繰り返すうちに、同じ条件下で起こる行動がパターンとして定着してしまいやすい、という特徴があります。
ですから、このような場合はいっそ、おうちの周りを歩かない、ということも一つの手です。
自転車や車で少し離れたところまで移動し、あまり馴染みのない場所から歩行をする、そして再び自転車や車で自宅まで戻るのです。
特に山を歩くことをお薦めします。
山歩きは、こだわりの多い発達障害のお子さんたちにとって、こだわりになるようなものが少なく、静かに淡々と歩くのにもってこいのトレーニングです。
お休みの日には山の麓まで行き、歩行をスタートしてみてはいかがでしょうか。
お休みの日には山の麓まで行き、歩行をスタートしてみてはいかがでしょうか。
③こだわりを回避しながら歩かせる時の対応のポイント
自宅の周り以外を歩きましょう、とは言っても、こればかりしていても自宅付近や街中をお母さんと手を繋いで歩くことにはつながりません。
次の段階では、家の周りを歩くことを練習しなくてはなりません。
最初は一時的に好きなもの(お菓子やジュース・おもちゃ・携帯の動画など)で気を引いても良いです。
Y君の場合は室外機が見えるぞ、というタイミングで好きなものを見せたり口に入れたりすることで、
こだわりスイッチが入る前に別のものに注意を向けているうちに、さっと小走りで通り過ぎてしまうことが重要です。
こだわりスイッチが入る前に別のものに注意を向けているうちに、さっと小走りで通り過ぎてしまうことが重要です。
また、大人と子どもの歩く位置にもコツがあります。
室外機は道路の住宅側にあるので、住宅側を大人、車道側を子どもという形で歩きましょう。
手をつないだ状態で、大人がY君の半歩前を歩くことで大人が壁となり、こだわりの室外機が目に入りづらくなります(図1)。

手をつないだ状態で、大人がY君の半歩前を歩くことで大人が壁となり、こだわりの室外機が目に入りづらくなります(図1)。

実は手のつなぎ方にもコツがあります。
飛び出させまいと、手を力強く握ってはいないでしょうか。
手を強く繋げば繋ぐほど、手放しは起こりやすくなります。
さりげなく、力を抜いて手を繋ぐように心がけましょう。
それでも手放ししてしまう場合、まずは手首を軽く握るでも良いですし(手の平の接触による反射なので、手首を持つ方が手放しは出にくいです)、
もぞもぞと手が動いてきてしまうようなときに、反対の手に繋ぎ替えることでやり過ごせる場合もあります(図2)。

もぞもぞと手が動いてきてしまうようなときに、反対の手に繋ぎ替えることでやり過ごせる場合もあります(図2)。

④「めまい刺激」に注意 正しい目の使い方を覚えさせる
自閉症のお子さんの中には、Yくんのようにくるくると回るもの(扇風機や洗濯機の動き、床屋のクルクルなど)を見たがるお子さんが多くいます。
この行動は、「めまい刺澈」を求める、日の常同行動のようなものです。
好きだから、とその行動を認めていると、目的的にものを見て情報を取り入れる(注視)という、本来の目の使い方へと発達していきません。
それだけでなく、自己刺激的な目つむりや発作につながる場合もあります。
ですから、このようなお子さんには正しい目の使い方を学習させる必要があります。
そのためには、歩行トレーニングと並行して、学習や作業課題を行うことが有効です。
生活の中で正しく目を使って手を動かす時間を作り、良い日の使い方をしている時間をできるだけ長くしてあげましょう。
シール貼りやビーズ通しなどの手作業や、ペンを持って線を引く(ぐるぐるとなぐり書きをするのではなく、直線ひきや迷路、2点結びなど、
見て、考えて手を動かすことが大切)などの学習課題に取り組むと、目の使い方が変わってきます。
見て、考えて手を動かすことが大切)などの学習課題に取り組むと、目の使い方が変わってきます。
また、テレビやタブレットを見るときも、少し距離をとって画面を見られるよう練習していきましょう。
この記事をご紹介したのは…
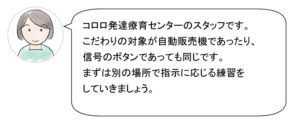
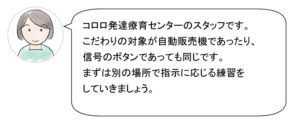
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




