〈コラム〉自傷の出にくい身体づくりと、予兆の見極めを
発達プログラム166号問題行動はもう始まっている part2 ー問題行動のメカニズム/直前刺激の見極めー「問題行動Q&A」より
Q
特別支援学校教諭です。
小学部3年のある男子児童は、何か気に入らないことがあると腕を噛んだり、顔を叩いたりする自傷があり、対応に困っています。
彼は着席して話を聞くのは苦手ですが、ずっと不機嫌なわけではなく、機嫌が良い時は友達の周りをぐるぐる回っていたり、
元気よくジャンプしていたりして、教室内でみんなと過ごすことができています。
しかし、急に大きな叫び声をあげて、自傷が出てしまうことがあり、
何か気に入らないことがあるのを訴えているのではと思っています。
ストレスがかかることは避けてあげたいとは思いますが、学校の活動でしなければいけないことも多く、
どうしたらいいかと困っています。
コロロではこのようなお子さんに対し、どう対応されていますか?
A
顔たたきは、失明やあご・頬骨の変形にも繋がります。
このお子さんの将来のことを考えると、危機感を持って、自傷の出にくい身体づくりを早期からする必要があります。
また、正しく原因を理解し、適切なプログラムを行うことができれば、自傷行動は減少します。
まずはどのような原因が考えられるかまとめてみましょう。
初めに、本号の提言(P2~5)に書かれている通り自傷行動には予兆があり、
予兆状態の時に何かしらの刺が入ると自傷行動に繋がります。
表情がニコニコしていたり身体が揺れていたり、突然立ち上がってピョンピョン跳ねたり…・・。
一見楽しそうな様子にえるこれらの行動も、実は予兆状態であり自傷が起きやすい状態と言えます。
また、予兆状態の時は意識レベルが低下している状態でもあります。
意識レベルが低下しているときに不用意な接触、ちょっとした声かけなど少しの刺が入るとパニックや自傷行動が出てしまいます。
コロロでもこのお子さんと同じように顔たたきなどの自傷行動が出やすいC君というお子さんがいます。
C君の意識レベルが下がっている時に見られやすい身体の動きとして、以下のものが挙げられます。
①口が半開きで舌が出ている
②上半身が屈曲していて、座っていると身体が前後に揺れる
③肘が屈曲していて、手を口に入れたり髪の毛を触ったり、手をひらひらさせる動きがある
こういった行動が出ている時に不用意に声かけをすると、大きな声が出て自傷行動に繋がることが多いです。
また、活動の様子を観察してみると、不用意な声かけだけが刺になるのではなく、
他にも自傷行動を引き起こしてしまう直前刺邀がありました。
例えば、「同じグループ内に泣いているお子さんがいる」というような音刺潔、行動を促そうとして体に触る接触刺激などです。
自傷行動を減らしていくためには、
「意識レベルが下がりにくい身体づくり」と「不用意な対応をしない」という2点が必要になります。
まずは意識レベルが下がりにくい身体づくりを目指し、徹底的に歩きました。

手繋ぎ歩行
コロロでは動と静のプログラムを適宜切り替えながら行っていきますが、多動傾向が強かったので、
動のプログラムを増やし、手繋ぎ歩行で一定ペースを保って歩き続けることを室内でも屋外でもしっかり行っています。
その際、先程述べた意識レベルが下がっている時の行動に気をつけることの他に、手繋ぎの様子も観察しています。
手繫ぎが段々と甘くなっていると淡々と歩けていても意識レベルは下がっている状態です。
このような時に声を不用意にかけてしまうと、自傷に繋がってしまっていました。
一見落ち着いているように見える時こそ、要注意です。
落ち着いていると思って、大人がタイミングを見ずに声かけや接触をしてしまい、状態を崩すこともあります。
ですので、表情の変化や手繋ぎの様子に気をつけ、
完全に意識レベルが下がり切る前に「手を繋いでね」や「前だよ」、
倍号待ちで「気をつけ」などこまめに指示をして意識レベルの低下を防いでいます。
また、繋いでいないほうの肘が曲がって口や髪を触り出すことがあるので、
片手に手提げ袋などの荷物を持たせることも効果的でした。
しっかり身体を動かした後は、静のプログラムとして行動トレーニング(正座、立位、まぐろさんなど一定時間同じ姿勢を保つ)を行っています。

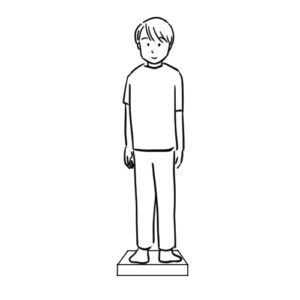
正座 立位
入会当初は、姿勢の保持が難しかったので、1分ずつ、100カウントなど短い時間から始めました。
そして初めは、小さな身体の揺れや肘の屈曲があっても、大きく姿勢が崩れなければOKとし、不用意な刺激を入れないようにして、徐々に肘を屈曲させないこと、無目的な身体の動きを抑制させることを意識してこまめに指示をしていきました。
コロロに通い始めたばかりの頃は意識レベルが下がりやすく、声出しや自傷行動が頻繁に出ていたC君。
現在も自傷行動が全く出ないというわけではありませんが、
1時間一定のペースで歩くことやスタッフの声かけで手の動きや肘の屈曲や自分で
少しずつ直すことができるようになってきています。
自傷などの問題行動は出る前に必ず予兆となる行動が現れます。
お子さんの状態をよく観察し、適切な対応と、問題行動が出にくい身体づくりを継続して行っていきましょう。
この記事をご紹介したのは…
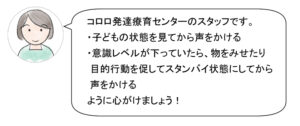
「自傷の出にくい身体づくりと、予兆の見極めを」の記事をご紹介します。
Q
特別支援学校教諭です。
小学部3年のある男子児童は、何か気に入らないことがあると腕を噛んだり、顔を叩いたりする自傷があり、対応に困っています。
彼は着席して話を聞くのは苦手ですが、ずっと不機嫌なわけではなく、機嫌が良い時は友達の周りをぐるぐる回っていたり、
元気よくジャンプしていたりして、教室内でみんなと過ごすことができています。
しかし、急に大きな叫び声をあげて、自傷が出てしまうことがあり、
何か気に入らないことがあるのを訴えているのではと思っています。
ストレスがかかることは避けてあげたいとは思いますが、学校の活動でしなければいけないことも多く、
どうしたらいいかと困っています。
コロロではこのようなお子さんに対し、どう対応されていますか?
A
顔たたきは、失明やあご・頬骨の変形にも繋がります。
このお子さんの将来のことを考えると、危機感を持って、自傷の出にくい身体づくりを早期からする必要があります。
また、正しく原因を理解し、適切なプログラムを行うことができれば、自傷行動は減少します。
まずはどのような原因が考えられるかまとめてみましょう。
自傷行動の原因分析
初めに、本号の提言(P2~5)に書かれている通り自傷行動には予兆があり、
予兆状態の時に何かしらの刺が入ると自傷行動に繋がります。
表情がニコニコしていたり身体が揺れていたり、突然立ち上がってピョンピョン跳ねたり…・・。
一見楽しそうな様子にえるこれらの行動も、実は予兆状態であり自傷が起きやすい状態と言えます。
また、予兆状態の時は意識レベルが低下している状態でもあります。
意識レベルが低下しているときに不用意な接触、ちょっとした声かけなど少しの刺が入るとパニックや自傷行動が出てしまいます。
コロロでもこのお子さんと同じように顔たたきなどの自傷行動が出やすいC君というお子さんがいます。
C君の意識レベルが下がっている時に見られやすい身体の動きとして、以下のものが挙げられます。
①口が半開きで舌が出ている
②上半身が屈曲していて、座っていると身体が前後に揺れる
③肘が屈曲していて、手を口に入れたり髪の毛を触ったり、手をひらひらさせる動きがある
こういった行動が出ている時に不用意に声かけをすると、大きな声が出て自傷行動に繋がることが多いです。
また、活動の様子を観察してみると、不用意な声かけだけが刺になるのではなく、
他にも自傷行動を引き起こしてしまう直前刺邀がありました。
例えば、「同じグループ内に泣いているお子さんがいる」というような音刺潔、行動を促そうとして体に触る接触刺激などです。
自傷行動を減らしていくためには、
「意識レベルが下がりにくい身体づくり」と「不用意な対応をしない」という2点が必要になります。
身体づくりは歩行トレーニングから
まずは意識レベルが下がりにくい身体づくりを目指し、徹底的に歩きました。

手繋ぎ歩行
コロロでは動と静のプログラムを適宜切り替えながら行っていきますが、多動傾向が強かったので、
動のプログラムを増やし、手繋ぎ歩行で一定ペースを保って歩き続けることを室内でも屋外でもしっかり行っています。
その際、先程述べた意識レベルが下がっている時の行動に気をつけることの他に、手繋ぎの様子も観察しています。
手繫ぎが段々と甘くなっていると淡々と歩けていても意識レベルは下がっている状態です。
このような時に声を不用意にかけてしまうと、自傷に繋がってしまっていました。
一見落ち着いているように見える時こそ、要注意です。
落ち着いていると思って、大人がタイミングを見ずに声かけや接触をしてしまい、状態を崩すこともあります。
ですので、表情の変化や手繋ぎの様子に気をつけ、
完全に意識レベルが下がり切る前に「手を繋いでね」や「前だよ」、
倍号待ちで「気をつけ」などこまめに指示をして意識レベルの低下を防いでいます。
また、繋いでいないほうの肘が曲がって口や髪を触り出すことがあるので、
片手に手提げ袋などの荷物を持たせることも効果的でした。
しっかり身体を動かした後は、静のプログラムとして行動トレーニング(正座、立位、まぐろさんなど一定時間同じ姿勢を保つ)を行っています。

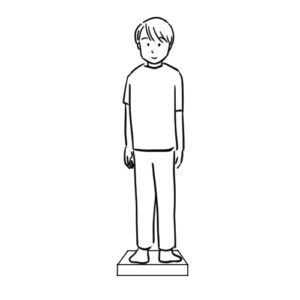
正座 立位
入会当初は、姿勢の保持が難しかったので、1分ずつ、100カウントなど短い時間から始めました。
そして初めは、小さな身体の揺れや肘の屈曲があっても、大きく姿勢が崩れなければOKとし、不用意な刺激を入れないようにして、徐々に肘を屈曲させないこと、無目的な身体の動きを抑制させることを意識してこまめに指示をしていきました。
コロロに通い始めたばかりの頃は意識レベルが下がりやすく、声出しや自傷行動が頻繁に出ていたC君。
現在も自傷行動が全く出ないというわけではありませんが、
1時間一定のペースで歩くことやスタッフの声かけで手の動きや肘の屈曲や自分で
少しずつ直すことができるようになってきています。
自傷などの問題行動は出る前に必ず予兆となる行動が現れます。
お子さんの状態をよく観察し、適切な対応と、問題行動が出にくい身体づくりを継続して行っていきましょう。
この記事をご紹介したのは…
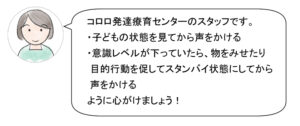
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




