高機能自閉症児のこだわり「食べ物を残してはいけません」の記事をご紹介します。
「食べ物を残してはいけません」
「人にはそれぞれの理由があります」
「汗をほとんどかいていないから着替えなくて大丈夫です」
「手がきれいになるまでしっかり手洗いします」。
こう言われた時、皆さんはどう返しますか?
この言葉だけを見ると何の問題も無く思えます。
しかし一見、正論に思えても、そこには自閉症特有の問題が隠れていることが多いのです。
「食べ物を残してはいけない」と主張したV君、その時の状況は・・・。
V君のお昼ご飯は、いつも自分の好きな食べたい物を買ってきます。
ある日、たまたま見つけた餃子12個とごはんをお昼ご飯に持ってきました
(紙面の関係上、間の細かいやりとりは省きますが、実際に言葉を交わしていた時間は10~15分くらいです)。
(紙面の関係上、間の細かいやりとりは省きますが、実際に言葉を交わしていた時間は10~15分くらいです)。
私「餃子、ちょっと多いんじゃない?」
V君「いや大丈夫です。食べられますよ。もったいないですし」
私「(いや・・・そういう意味じゃなくて)ちょっと量が多すぎるから、5個減らそうか」
V君「え?何でですか?何で12個食べちゃいけないんですか?僕が買ったんですよ。
それに食べ物を残したら食糧廃棄量が増えて問題になっているんですよ。いいんですか?環境問題ですよ!」
それに食べ物を残したら食糧廃棄量が増えて問題になっているんですよ。いいんですか?環境問題ですよ!」
私「・・ええ~っと、じゃあそのお金は誰からもらったの?」
V君「・・お母さんですよ。それが何か?僕のウチのお金ですから!」
私「じゃあ決定権はお母さんにあるよね。お母さんのお金だから。お母さんに確認します」
(実際にご家族にお電話して確認しました)
私「お母さんも餃子残した方がいいって言っていました。だから5個残しましょう」
V君「ええええ。もうだって先生のお金じゃないじゃないですか。
餃子もそんなに大きくないし(実際は普通よりも少し大きめの餃子)、残したらもったいないじゃないですか」
餃子もそんなに大きくないし(実際は普通よりも少し大きめの餃子)、残したらもったいないじゃないですか」
私「・・・じゃあ減らすのは3個にします」
(5個減らすのは無理だと判断。言葉で反論せず黙って餃子を3個減らす。そしてその餃子を持ってV君のそばから離れる)
(5個減らすのは無理だと判断。言葉で反論せず黙って餃子を3個減らす。そしてその餃子を持ってV君のそばから離れる)
20分後・・・観念したようにV君は餃子を静かに食べ始めました。
その部屋にいた他のスタッフはV君と私のやりとりを見て、V君に声かけせず、周囲も食事をしている状態を続けてくれていました。
実際、お昼ご飯に餃子12個とご飯を食べてはいけないか?と聞かれれば、別に問題はありません
(食べすぎの習慣化により、肥満やその他の病気の心配はありますが)。
(食べすぎの習慣化により、肥満やその他の病気の心配はありますが)。
ではなぜ私が餃子を減らすことにこだわったかというと、V君の「餃子を12個食べたい」という訴えが、
マイルールや一度決めたことが変更できないという彼の基本障害から発生したことだと判断したからです。
マイルールや一度決めたことが変更できないという彼の基本障害から発生したことだと判断したからです。
彼の日常生活はこのマイルールが変えられないということにより、常にご家族やお友達との評いが絶えません。
その時の暴言は、ご家族が「堪えきれなくて、部屋を出てきてしまいました」とおっしゃるくらい、とても激しいものです。
ああ言えばこう言うといった感じで、彼自身の中では理屈が通っているのです。
このような場合、周囲の大人はどうすべきでしょうか?
わかるまで言い聞かせる?だんだんわかってくるから今は大目に見ておく?無理やりにでも言うことを聞かせる?
これらの方法は全くうまくいきません。
どの方法も「大人がどうするか」ということだけに注目して、
「子どもがどういう状態か」という観察と分析や結果どうなったかの視点が全くないからです。
「子どもがどういう状態か」という観察と分析や結果どうなったかの視点が全くないからです。
では、どうしたらいいか?
どうやってV君のマイルールの1つを崩したか、
以下のようなポイントでV君の行動を観察・分析して、対応をしました。
どうやってV君のマイルールの1つを崩したか、
以下のようなポイントでV君の行動を観察・分析して、対応をしました。
①姿勢(意識レベル)の確認
この時、昼食前だったのでV君はきちんと正座をしていました。
姿勢が崩れていたり、寝転んでいたり、多動の時は、姿勢を整えたり、姿勢が戻るタイミングを見計らって声をかけます。
②声のトーンの確認
興奮をすると早口、多弁、高い声になります。
その時に、大人が同じようなトーンで畳みかけて反論してもうまくいくことはありません。
大人はいつもよりも意識的に、ゆっくり、言葉は少なく、低めの声で話します。
③事実を論点にする
食料廃棄率という言葉が出てきましたが、ここでは論点にしません。
事実の確認がこの場でできないからです。
地球温暖化、少子化など社会問題について話す発達障害の子どもは多いのですが、
学習場面でどれくらい本当に理解できているかチェックをすることは必要です。
学習場面でどれくらい本当に理解できているかチェックをすることは必要です。
また、論点は1つに絞った方がうまくいくことが多いように思います。
④着地点の調製
もし私が餃子を5個減らすことにこだわっていたら、V君の反論は続いていたかもしれません。
この時はこちらが5個→3個に減らすことによって、V君の反応が変わるかどうか試してみました。
大人が最初に決めた通りに絶対しなくてはいけないということにこだわりすぎてしまうと、
結果的に反発を強めてしまうことがあります。
結果的に反発を強めてしまうことがあります。
試した結果どうなっているか、その都度確認しながら対応をしましょう。
無理だと思ったら、着地点の調整が必要です。
無理だと思ったら、着地点の調整が必要です。
V君の餃子の例は一例ですが、周囲の人に合わせて変化を受け入れられるようにすることは、
今の生活を安定させていくためにも、将来仕事をするためにも非常に重要なことです。
今の生活を安定させていくためにも、将来仕事をするためにも非常に重要なことです。
なぜなら、マイルールに縛られて変化を受け入れられなければ、新しいスキルを学ぶことができないからです。
反発をすることを繰り返していて、年齢とともにだんだん理解ができるというのは幻想です。
マイルールを変更して別の方法を受け入れられたという経験が繰り返し必要です。
それは例えば、着替えと歯磨きの順番を逆にしてみるなどの小さな変更かもしれません。
しかし、そのような日常生活の小さな変化を受け入れることを沢山経験することによって、子ども達の行動は変わっていくのです。
V君はマイルールにとらわれていない時、年齢よりも大人びていて、小さい子やスタッフへの配慮もあるお子さんです。
スタッフの様子を見て、
「本当にコロロの先生って大変だな~。先生たち本当にすごい」と言ったり、
お友達が「実は先生たちのことがずっと嫌いでした」と言った時に、
「そういうことは面と向かって言っちゃいけないと思うな~」と言ったり、
周囲を見て、社会的なルールが理解できています。
「本当にコロロの先生って大変だな~。先生たち本当にすごい」と言ったり、
お友達が「実は先生たちのことがずっと嫌いでした」と言った時に、
「そういうことは面と向かって言っちゃいけないと思うな~」と言ったり、
周囲を見て、社会的なルールが理解できています。
彼のこういった素直で良い面を伸ばしつつ、変化を受け入れられる力も伸ばして行きたいと思っています。

この記事をご紹介したのは…
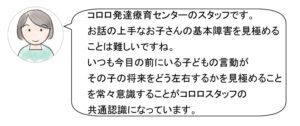

この記事をご紹介したのは…
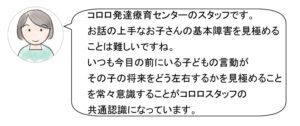
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




