こんなときどうする?②より
「気持ちを落ち着かせる方法を教える」の記事をご紹介します。
困った行動への対応法として、「〇〇しません」「静かにします」などのことばを
言わせるだけ・書かせるだけではほとんど効果がないと実感しています。
言わせるだけ・書かせるだけではほとんど効果がないと実感しています。
問題行動の改善にことばを用いる際、音や意味を教える・覚えさせることだけでなく、
ことばと適切な行動(力が抜けた、表情が柔らかくなった、静かになったなど)をいかにマッチングさせるか、という点が重要です。
そのためには、どのような方法が有効でしょうか?
Lさんの事例をご紹介いたします。
中学生のLさんは、学習や歩行など目的がはっきりした時間は落ち着いているのですが、
待ち時間や場面の切り替え時には、すぐに意識レベルが下がり、不穏な状態に陥ります。
そういったとき、大人が「手はお膝です」「口を閉じて」などの注意ことばを使用すると、
身体をかきむしり大きな声を出すことも時々見られていました。
明らかに注意ことばと不快反応がマッチングされている様子でした。
改めて別のことばを選定し、そのことばと適切な行動(力が抜けた、表情が柔らかくなったなど)とをマッチングさせようと考え、
今回は「穏やかに」ということばについて学習をしました。
まず、「穏やかに」ということばだけでなく、その時の表情や仕草も含めてパターニングすることにしました。
学習の中で、笑い顔・泣き顔・怒り顔などの表情について練習し、”笑顔+「穏やかに」”という表現の仕方をパターニングしました。
また、イライラしてくると、指先をカリカリとこすり合わせる動きがあったので、手を胸に当てて「穏やかに」というポーズも併せて教えました。
タイミングも重要です。
すでに力こもりや大きな声を出している際にことばを教えようとしても、そのことが悪い刺潔になり、
問題行動をエスカレートさせてしまうこともあります。
Lさんの場合、顔が下がり始めた・独り言が出始めた、というくらいのタイミングで、
私から「おだ・・・」などのヒントを出して「穏やかに」と顔を上げさせるようしました。
このような練習を何度かしていくうちに、私が目を合わせると、
彼女自ら胸に手を当て「穏やかに」と言って、ニコッと私に微笑みかけてくれるようになりました。


その行動の後は意識レベルが少し上がり、しばらくは良い状態を維持できました。
一方で、状態によっては「穏やかに!!!」と言いながらも、とても興奮しており、全く穏やかでない状態のときもあります。
そうした時は、ことばが全く機能していないと考え、別の方法を使用し、気持ちを切り替えるよう促しています
(指さしやジェスチャーなどの音声を使用しない方法、「ごみを捨ててきて下さい」など他の目的行動を促すなど)。
Lさんは「穏やか」ということばについて概念的に深く理解して使用しているわけではありません。
いわゆる呪文のようなものだと考えています。
「穏やかに」=顔が上がる・大人と目が合う・独り言が止まる(適切な行動)、というパターニングをしたことで、
より良い行動に結びついたのです。
他にも、気持ちを落ち着かせる学習の例をご紹介します。
①深呼吸を教える
個別学習の中で「3秒で吸って3秒で吐く(ゆっくり深呼吸)」を練習しました。
呼吸を整える目的もありますが、深呼吸=良い行動、とパターニングするため、
「深呼吸したら、〇ですか、xですか」「深呼吸と大きな声を出す、どっちがOですか?」なども併せて、学習しました。
少し不穏になってきた時、「深呼吸は?」と声かけすると、深く呼吸ができるようになりました。
②「まあいいか」「どっちでもいいです」などのことばを教える
Lさんは、自分の要求が通らないと怒り出すこともあったので、日頃からユアペースを徹底しながら、「まあいいか」ということばを教えました。
今日はしまじろうのDVDは見られません。
なんて言いますか。
(まあいいか)
その後、実際に動画鑑賞の場面を設定し、見たいDVDが見られなくても「まあいいか」と言って
怒らずにいられたという経験を積み重ねていきました。
また、私と学習することにもこだわりがあったLさんに、「どっちでもいいです」ということばを教えました。
今日は大塚先生と学習しますか、それとも神村先生と学習しますか。
(どっちでもいいです)
この場合も、実際の学習場面で同様の出題をし、「では今日は神村先生と学習しましょう」となっても怒らずに学習できた、という経験を重ねていきました。
このように、プリント学習だけ、口頭での質問だけで終わらせることなく、適切な行動が実行できることまで含め、パターニングすることが大切です。
”どのようなことを教えたら、その子がより生きやすくなるだろうか”という視点を忘れずに、これからも教材や教え方を工夫していきたいと考えています。
この記事をご紹介したのは…
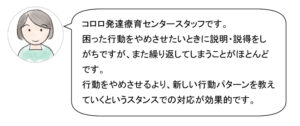
この記事をご紹介したのは…
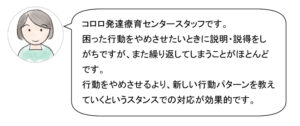
1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、
現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。
コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。
幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。
コロロメソッドとは
コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
コロロ発達療育センター
コロロ学舎




